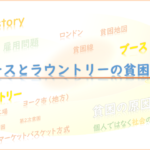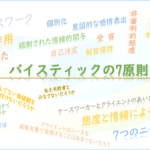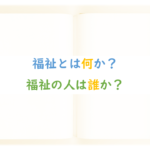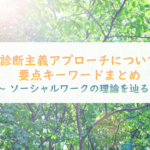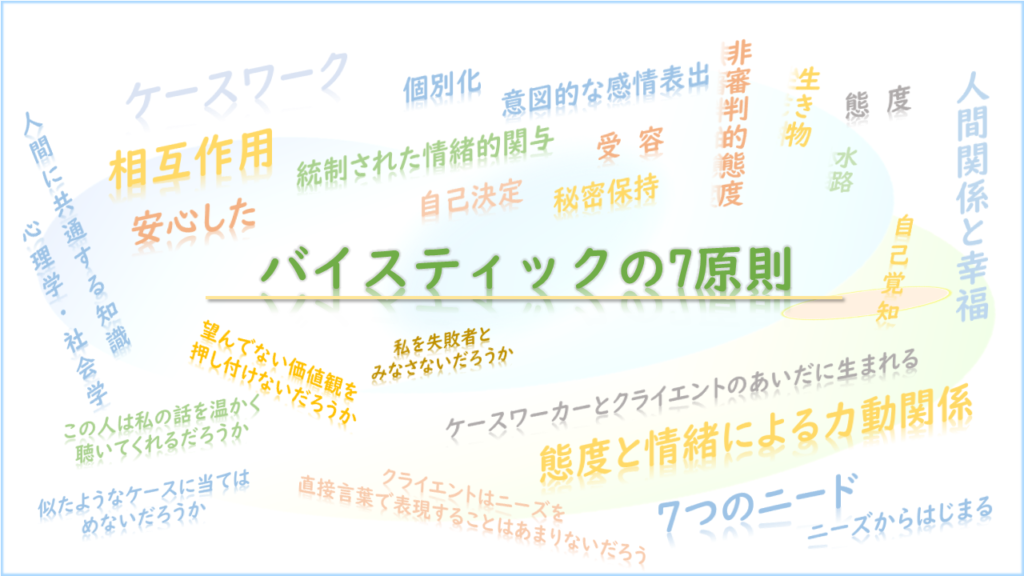

はじめに
本記事では、F.バイスティックが提唱した「バイスティックの7原則」について、援助関係の本質という視点から、「医療・介護・福祉・保育従事者」に向けて現場に活かすことのできる知識としてまとめてあります。
バイスティックの7原則は、もともとケースワーカーの面接技法として広まった考え方になりますが、現在では医療や介護、福祉や保育でも取り扱われております。今では社会福祉士や精神保健福祉士のみならず、介護福祉士や保育士のテキストにも出てくるぐらいです。
ただ、このバイスティックの7原則は「援助関係」という視点から、もう少し深いところを知ることで、より一層現場に役立つ知識とさらに大きく生まれ変わります。
そのため、本記事では専門書を参考に、他のブログや教科書では触れられていない「もう一歩先のバイスティック」を紹介しております。
本記事の目的や対象
・クライエントとの信頼関係の大切さに気付く
・クライエントのニードを知る
・面接や支援に役立つ価値観や知識を学ぶ
・社会福祉士や精神保健福祉士、介護福祉士や保育士のレポートや試験対策
#バイスティックの7原則、#簡単にわかりやすく、#現場に活かす、#自己覚知、#援助関係、#ケースワーク、#ソーシャルワーク、#ソーシャルワーカー、#社会福祉士、#精神保健福祉士、#介護福祉士、#看護師、#保育士、#レポート、#面接技法、#イラスト
バイスティックの原則で触れられている「価値観」は、面接技術のみならず、対人援助全般に役に立つことは間違いありません。
それでは以下まとめていきます。
援助関係を形成する目的
バイスティックと聞くと、7つの原則が最初に思い浮かばれます。
しかし、実は援助という目的を達成するための手段である「援助関係」に着目した点も重要になってきます。
以下援助関係について引用になります。
援助関係とは
ケースワーカーとクライエントのあいだで生まれる、態度と情緒による力動関係である。
そして、この援助関係は、クライエントが彼と環境のあいだにより良い適応を実現してゆく過程を援助する目的をもっている。
引用:ケースワークの原則 誠信書房 P17より
援助関係の目的とは
クライエントが調査や診断、あるいは治療の過程に安心感をもって、また効果的に参加してゆけるような雰囲気や環境を援助のなかにつくること。
引用:ケースワークの原則 誠信書房 P18より
このように、援助関係はケースワークの魂とも言われております。
クライエントの抱える問題を解決していくにあたって、援助関係というものは、より良い支援や援助を行う上で不可欠ともいえます。
きっとバイスティックの姿勢は、面接技術としてのみならず、施設や事業所といった現場で活躍する実践者にとっても、大切な視点を教えてくれるものとなっております。
援助関係で役に立つこと
クライエントへの援助を行うにあたって、心理学や社会学などの知識があるとより専門的な援助を行うことができるとも言えます。
このように、クライエントのニーズや問題を改善していくにあたって、「人間関係に関する科学的な知識」が必要と言われております。
バイスティックは、著書ケースワークの原則の最初にこのような言葉を述べております。
※以下「ケースワークの原則」P3~4引用・抜粋
個人を理解する上で役立つこと
人間に共通するさまざまな特徴をできるかぎり知っていること。
クライエント理解で役立つこと
・パーソナリティがどのように発達して変化するのか。
・パーソナリティが生活上のストレスにいかに反応するのか
※正常な反応も異常な反応も含めて。
このように、「人間に共通する知識」や、「一人ひとりのクライエントをより良く理解する上での知識」は、援助関係を形成する上で必要なものとされております。
社会福祉に関わる人にとって、心理学や社会学といった知識がなぜ必要なのか?という問いに対する答えとも言えるかもしれません。
人間関係と幸福について
バイスティックは、「人間関係と幸福」についても触れております。
幸せについて
・この世でもっとも豊かな人は、真の友人をたくさんもつ人(古いことわざ)
・家庭における幸福:豊かであり満足できる家族関係。
・生産的で良好な職場:従業員同士、経営者と従業員の関係が良好であることが要素の一つ。
不幸せについて
貧しい人間関係こそ、人に不幸をもたらす源泉。
※例)貧しい親子関係→パーソナリティに外傷を与える。
※例)精神医学では、貧しい人間関係が神経症や精神病の基礎要素になる。
このように、バイスティックは幸せや不幸せについて、人間関係が関係することを改めて気づかせてくれます。
「貧しい家庭が必ずしも不幸でもなければ、裕福な家庭が必ずしも幸せとは限らない」のです。
+α~Wellbeing
・Having(その人がもっているもの)をとって、とって最後に残るものは何か?
・Being(その人の存在)が残る。
・Beingに「Well」をつけてあげる。
・Well-Beingになる。
今社会福祉に限らず、「Wellbeing」という言葉がよく出てくるような世の中になってきました。
死生学を日本で広めたアルフォンスデーケンも、「若いうちは所有というものを重視するが、年老いていくと内面が重要になってくる」という言葉を述べております。
真の幸福というものは、物を所有したり使用する中にはないものと言われております。
物それ自体が、快適さや満足さを与えることはあるが、実は「満足のゆく人間関係が促進されること」がなければ、間接的に幸福に寄与することはないとのことです。
このように「人間関係と幸福」についてもバイスティックは述べております。
7つのニーズ
バイスティックは、心理社会的問題を抱えているクライエントには共通のニーズがあることを述べております。
以下7つのニーズの紹介になります。
7つのニーズ(1)
クライエントは、ケースとしてではなく、一人の個人として迎えられ、対応して欲しいと望んでいる。
7つのニーズ(2)
クライエントは、否定的な感情と肯定的な感情のどちらも表現する必要性をもっている。
7つのニーズ(3)
クライエントは、弱さや欠点、失敗をもっていても、一人の価値ある人間として、あるいは生まれながら尊厳をもつ人間として受け止められたいというニードをもっている。
7つのニーズ(4)
クライエントは、感情表現に対して共感的な理解と適切な反応を得たいと望んでいる。
7つのニーズ(5)
クライエントは、陥っている困難について、一方的に非難されたり、叱責されたくはないと考えている。
7つのニーズ(6)
クライエントは、自分の人生に関する選択と決定を自ら行いたいとするニードをもっている。
7つのニーズ(7)
クライエントは、自分に関する内容の情報をできる限り秘密のままで守りたいというニードをもっている。
このように、上記はこの後の7つの原則の内容に繋がります。
実は「ニーズが先にあって原則がある」という流れが本来のバイスティックの考え方になります。
また、クライエントはこれらのニーズを「直接言葉で表現することはあまりないだろう」述べております。
援助者は、言葉以外にある情緒や態度から情報を得る感受性の豊かさも必要不可欠です。
それが力動的な相互作用のはじまりとなっていくのです。
相互作用の3つの方向
バイスティックは援助関係において、態度と情緒による力動的な相互作用と述べております。
以下、援助関係について振り返りとなります。
援助関係とは
ケースワーカーとクライエントのあいだで生まれる、態度と情緒による力動関係である。
そして、この援助関係は、クライエントが彼と環境のあいだにより良い適応を実現してゆく過程を援助する目的をもっている。
引用:ケースワークの原則 誠信書房 P17より
またこの力動的な相互作用は3つの方向性を持っているということで以下紹介になります。
第1の方向
クライエントのニード。
クライエントからケースワーカーに向けて発信される相互作用。
第1の方向は、クライエントのニードからはじまります。
またこの時に重要なのが、クライエントは自分の悩みを打ち明けなければならないことに伴って、不安や恐れを抱いているということです。
不安や恐れ
・この人は私の話を温かく聴いてくれるだろうか?
・私を失敗者やダメな人など見なさないだろうか?
・似たようなケースを提示して、当てはめないだろうか?
・望んでいない意見や価値観を押し付けないだろうか?
このようにクライエントは悩みと一緒に、恐れや不安も抱いております。
以上が第1の方向となります。
第2の方向
ケースワーカーの反応。
ケースワーカーからクライエントに向けられる相互作用。
第2の方向は、クライエントのニーズを受けて、今度はケースワーカーの反応や相互作用になります。
クライエントのニーズは、言葉のみならず態度でも伝えられます。
よってケースワーカーも、「態度を通して、ニーズを感知したことを伝える」ことが重要になります。
また、このような反応は最初から備わっているものではなく、「ケースワーク過程を通じて深まっていく生き物である」とバイスティックは表現されております。
以上が第2の方向となります。
第3の方向
クライエントの気づき
クライエントからケースワーカーへ発信される相互作用。(再び)
クライエントがケースワーカーに対して、自分を尊重してくれる姿勢や態度を取ろうとしていることに気づきはじめます。
そして、そのような反応を受け取ったことを今度は伝え返そうとします。
単純な言葉で表現すると「安心した」という形を言葉もしくは、態度にて表現します。
以上が第3の方向となります。
バイスティックの7原則
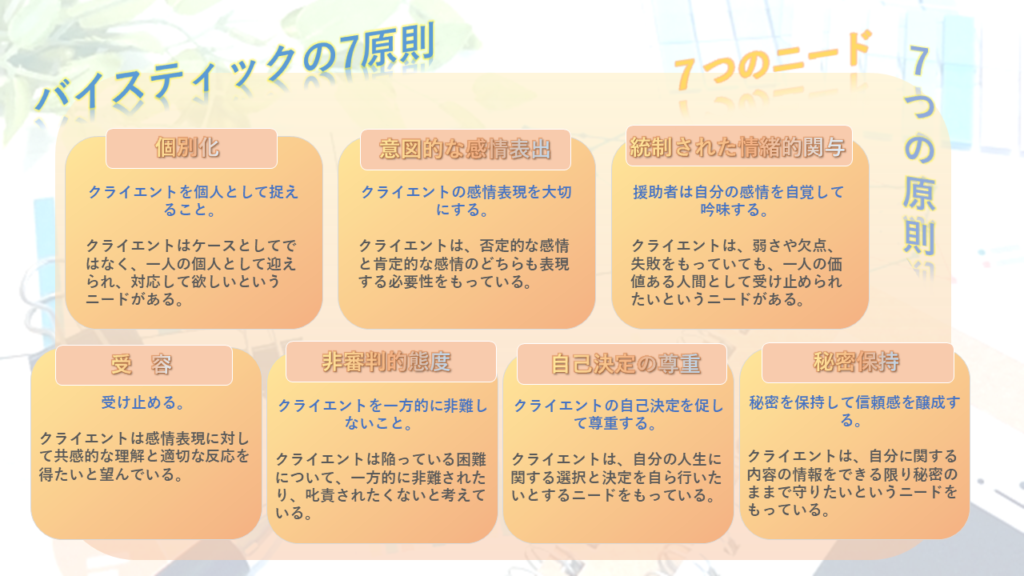
ここまで、「クライエントのニード」や「人間関係と幸福」について、「力動的な相互作用」について述べてきました。
これらを踏まえて以下7つの原則の紹介になります。
また、7つの原則はケースワーカーにとっての「行動規範」となります。そのため専門書を引用しながら以下確認していきます。
個別化
クライエントを個人として捉える。
7つのニーズ(1)
クライエントは、ケースとしてではなく、一人の個人として迎えられ、対応して欲しいと望んでいる。
クライエントを個人として捉えることは、一人ひとりのクライエントがそれぞれに異なる独特な性質をもっていると認め、それを理解することである。
ケースワークの原則 P36引用
以上が個別化の原則になります。
意図的な感情表出
クライエントの感情表現を大切にする。
7つのニーズ(2)
クライエントは、否定的な感情と肯定的な感情のどちらも表現する必要性をもっている。
クライエントの感情表現を大切にするとは、クライエントが彼の感情を、とりわけ否定的感情を自由に表現したいというニードをもっていると、きちんと認識することである。
ケースワーカーは、彼らの感情表現を妨げたり、非難するのではなく、彼らの感情表現に援助という目的をもって耳を傾ける必要がある。
そして、援助を進める上で有効であると判断するときには、彼らの感情表出を積極的に刺激したり、表現を励ますことが必要である。
ケースワークの原則 P54~55引用
以上が意図的な感情表出の原則になります。
統制的な情緒的関与
援助者は自分の感情を自覚して吟味する。
7つのニーズ(3)
クライエントは、弱さや欠点、失敗をもっていても、一人の価値ある人間として、あるいは生まれながら尊厳をもつ人間として受け止められたいというニードをもっている。
ケースワーカーが自分の感情を自覚して吟味するとは、まずはクライエントの感情に対する感受性をもち、クライエントの感情を理解することである。
そして、ケースワーカーが援助という目的を意識しながら、クライエントの感情に、適切なかたちで反応することである。
ケースワークの原則 P77引用
以上が統制された情緒的関与の原則になります。
受容
受け止める。
7つのニーズ(4)
クライエントは、感情表現に対して共感的な理解と適切な反応を得たいと望んでいる。
ケースワーカーが、クライエントの人間としての尊厳と価値を尊重しながら、彼の健康さと弱さ、また好感をもてる態度ともてない態度、肯定的感情と否定的感情、あるいは建設的な態度および行動と破壊的な態度および行動などを含め、クライエントを現在のありのままの姿で感知し、クライエントの全体に係ることである。
しかし、それはクライエントの逸脱した態度や行動を許容あるいは容認することではない。
つまり、受け止めるべき対象は、「好ましいもの」(the good)などの価値ではなく、「真なるもの」(the real)であり、ありのままの現実である。
ケースワークの原則 P113~114引用
以上が受容の原則になります。
非審判的態度
クライエントを一方的に非難しない。
7つのニーズ(5)
クライエントは、陥っている困難について、一方的に非難されたり、叱責されたくはないと考えている。
ケースワーカーは、クライエントに罪があるのかないのか、あるいはクライエントがもっている問題やニーズに対してクライエントにどのくらい責任があるのかなどを判断すべきではない。
しかし、われわれはクライエントの態度や行動を、あるいは彼がもっている判断基準を、多面的に評価する必要はある。
また、クライエントを一方的に非難しない態度には、ワーカーが内面で考えたり、感じたりしていることが反映され、それらはクライエントに自然と伝わるものである。
ケースワークの原則 P141引用
以上が非審判的態度の原則になります。
自己決定
クライエントの自己決定を促して尊重する。
7つのニーズ(6)
クライエントは、自分の人生に関する選択と決定を自ら行いたいとするニードをもっている。
クライエントの自己決定を促して尊重するという原則は、ケースワーカーが、クライエントの自ら選択し決定する自由と権利そしてニードを、具体的に認識することである。
また、ケースワーカーはこの権利を尊重し、そのニードを認めるために、クライエントが利用することのできる適切な資源を地域社会や彼自身のなかに発見して活用するよう援助する責務をもっている。
さらにケースワーカーは、クライエントが彼自身の潜在的な自己決定能力を自ら活性化するように刺激し、援助する責務をもっている。
しかし、自己決定というクライエントの権利は、クライエントの積極的かつ建設的決定を行う能力の程度によって、また市民法・道徳法によって、さらに社会福祉機関の機能によって、制限を加えられることがある。
ケースワークの原則 P164引用
以上が自己決定の原則になります。
秘密保持
秘密を保持して信頼感を醸成する。
7つのニーズ(7)
クライエントは、自分に関する内容の情報をできる限り秘密のままで守りたいというニードをもっている。
クライエントが専門的援助関係のなかでうち明ける秘密の情報を、ケースワーカーがきちんと保全することである。
そのような秘密保持は、クライエントの基本的権利にもとづくものである。
それはケースワーカーの倫理的な義務でもあり、ケースワーク・サービスの効果を高める上で不可欠な要素でもある。
しかし、クライエントのもつこの権利は必ずしも絶対的なものではない。
なお、クライエントの秘密は同じ地域福祉機関や他機関の他の専門家にもしばしば共有されることがある。
しかし、この場合でも、秘密を保持する義務はこれらすべての専門家を拘束するものである。
ケースワークの原則 P190引用
以上が秘密保持の原則になります。
ここまでバイスティックの7原則について紹介でした。
これらの原則は、援助という視点では要素となりますが、良好な人間関係を築くとなれば性質になるとのことです。
すなわち、面接のみならず「対人援助全般に通じるもの」と捉えることもできます。
もっと言えばバイスティックの原則は、人間関係に関わるもの全般に通じる(企業や組織、コミュニティなど)とも言えるかもしれません。
社会福祉士国家試験~設問より
社会福祉士国家試験で出題されたバイスティックに関連する問題を振り返ってみます。
それぞれ設問の内容が適しているかどうか確認してみましょう。
第29回-106.1
「自己決定の原則」は、クライエント自身や第三者に重篤な危害が及ぶことが想定される場合においても優先する。
第29回-106.2
「受容の原則」とは、ワーカーの個人的な価値観と一致する場合において、クライエントを受け止めることである。
第29回-106.3
「個別性尊重の原則」とは、他のクライエントと比較しながら、クライエントの置かれている状況を理解することである。
第29回-106.4
「非審判的態度の原則」とは、クライエントを一方的に非難したり、判断しないことである。
第29回-106.5
「統制された情緒的関与の原則」とは、クライエント自身が自らの情緒的混乱をコントロールできるようにすることである。
第34回-116.1
意図的な感情表出の原則とは、クライエントのありのままの感情を大切にし、その表出を促すことである。
第34回-116.3
個別化の原則とは、他のクライエントと比較しながら、クライエントの置かれている状況を理解することである。
第34回-116.4
受容の原則とは、ソーシャルワーカーがクライエントに受け入れてもらえるように、誠実に働き掛けることである。
第34回-116.5
非審判的態度の原則とは、判断能力が不十分なクライエントを非難することなく、ソーシャルワーカーがクライエントの代わりに意思決定を行うことである。
※このように第29回と第34回では似たような問題形式で出題されております。
社会福祉士国家試験~設問解答
以下それぞれについて解答になります。
第29回-106.1
「自己決定の原則」は、クライエント自身や第三者に重篤な危害が及ぶことが想定される場合においても優先する。
重篤な危害が及ぶことが想定される場合においてまで優先することはありません。命はなによりも優先されるものです。こちらは「言い過ぎ表現」となり不適切になります。
第29回-106.2
「受容の原則」とは、ワーカーの個人的な価値観と一致する場合において、クライエントを受け止めることである。
ワーカーの価値観ではなく、クライエント自身を人間として尊厳や価値を尊重して、ありのままの現実を受け止めることにあります。よって不適切になります。
第29回-106.3
「個別性尊重の原則」とは、他のクライエントと比較しながら、クライエントの置かれている状況を理解することである。
一人のケースとしてではなく一人の人として取り扱って欲しいというニーズがあるように、比較しながらという表現が不適切になります。一人ひとりのクライエントが独特の性質をもっているものと認識します。
第29回-106.4
「非審判的態度の原則」とは、クライエントを一方的に非難したり、判断しないことである。
こちらは適切な表現となります。Don't judgeという姿勢は、先入観に引っ張られずその人を捉える上でも重要になります。
第29回-106.5
「統制された情緒的関与の原則」とは、クライエント自身が自らの情緒的混乱をコントロールできるようにすることである。
クライエントではなく、ワーカーがクライエントの感情に適切な形で反応することが求められます。よって不適切になります。
第34回-116.1
意図的な感情表出の原則とは、クライエントのありのままの感情を大切にし、その表出を促すことである。
こちらは適切な表現となります。ありのままという表現があるように、肯定的な感情も否定的な感情のどちらも必要となります。
第34回-116.4
受容の原則とは、ソーシャルワーカーがクライエントに受け入れてもらえるように、誠実に働き掛けることである。
受容はワーカー自身がクライエントをありのまま受け止めるものです。よって不適切な表現となります。
第34回-116.5
非審判的態度の原則とは、判断能力が不十分なクライエントを非難することなく、ソーシャルワーカーがクライエントの代わりに意思決定を行うことである。
7つの原則のうち「自己決定の原則」に反する表現である点からも不適切な表現となります。ソーシャルワーカーはクライエントの声をアドボケイト(代弁)することはあっても、代わりに意思決定をするものではありません。
まとめ
以上が「バイスティックの7原則~援助関係の本質を探る」といった内容の紹介記事でありました。
良好な援助関係というものは、問題解決に向けて働きかけるため必須であるのみならず、根本的に援助を維持するためにも必要不可欠なものとなっております。
また、この援助関係は、必ずしも必要でない専門職もあります。
例えば外科医や歯科医、弁護士では、手術の成功や治療、訴訟に勝つことを目的とすれば、極論援助関係は不要です。
しかし、ケースワーカーにとっては援助関係は不可欠なものであり、専門職として独自性のある部分とも言えるのかもしれません。
※ちなみに最後ではありますが、ケースワーカーという言葉が一般的であった時代から、現代はソーシャルワーカーという言葉が一般的になります。しかし、現代も福祉事務所などでケースワーカーという表現が使われております。
ポイント
ケースワーカーにとって援助関係は不可欠なものである。
「バイスティックといえば7つの原則」だけではなく、その中にある大切なことを世の中に伝えたく、記事を書きました。
他にも弊サイトでは社会福祉の歴史や知識について、情報を提供していきますので、どうぞよろしくお願いします。
☆参考・引用文献
ケースワークの原則 援助関係を形成する技法 F・Pバイスティック著 尾崎新、福田俊子、原田和幸訳 誠信書房 P3~29
この本は大変有名な本であるため、一度は手に取ってみることをオススメします。